シリーズ『おしえて論文作成』では、論文作成における留意点を紹介していきます。
教えて論文作成 Part 10では、論文内で他者の研究について言及する際の注意点をご紹介します。
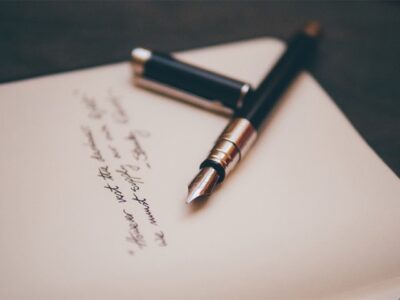
1.前回のおさらい
前回は「Part 9研究限界の書き方」としまして、研究の限界を考察することの重要性や、否定的な結果の上手な提示方法についてお話ししました。
★前回のコラムは、こちら↓★
https://届出.com/staff-blog/2023.03.08.1909/
どの論文にも研究限界が示されていますが、これは研究に何らかのミスはなかったのか、研究の方法に限界がなかったかを読者が判断できるようにするためです。したがって、事実を客観的に報告するべきであり、自分にとっては良くない結果だったとしても否定的な表現は使わないことが大切です。
また、自分の研究を過大評価、あるいは過小評価しないよう、研究限界が生じた理由や研究の結論への影響、必要に応じて対応策などを公正公平に記載しましょう。さらに、自分の研究は客観的にとらえ、研究成果の有用性や応用可能性、研究の将来の発展可能性など、肯定的な内容で締めくくるようにしましょう。
今回は、自分の主張を裏付けるにあたり、他者の研究に言及する際の注意点をご紹介いたします。
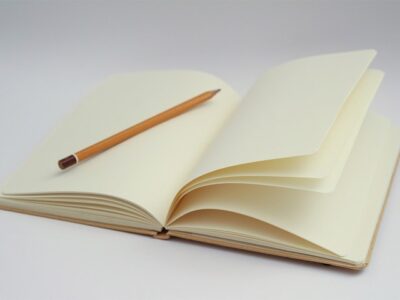
2.強調表現とヘッジング表現
はじめに、強調表現とヘッジング表現についてお話いたします。自分の主張を述べる際は、表現が直接的すぎると読者の反感を買う可能性があります。そこで、強調表現とヘッジング表現をうまく使い分けることが重要です。本シリーズの第11回でお話しましたように、強調表現を使うのは、研究成果や重要な情報など、注意を引き付けたい箇所が中心になります。
<Point ~強調表現を使うシチュエーション~ (第11回参照)>
- ・論文の中で研究成果を記述している箇所に読者の注意を引き付ける
- ・重要な情報を開示する際に短いセンテンスを使う
- ・重要な発見に注意を引き付ける際、一般的な問題について述べる時よりも力強い言葉を使う
一方、ヘッジングとは、明言や断言を避け、発現内容を和らげるという意味です。直接的な表現を避けることで、読者に対して疑問の余地を残し、尊大な印象を与えないようにすることができます。表現をあいまいにするのではなく、読者からの反論を防ぐために正確さを保つことが目的です。
<Point ~ヘッジング (明言や断言を避け、発現内容を和らげること) 表現>
- ・読者に対して疑問の余地を残し、尊大な印象を与えないようにする
- ・表現をあいまいにするのではなく、読者からの反論を防ぐために正確さを保つことが目的
次の章で、情報の確信の程度を調整する表現をご紹介します。

3.正確でわかりやすい用語を使おう
<Example~動詞>
- ・疑いの余地を全く与えない (研究結果の強調、文献への言及)
例1: These results demonstrate the importance of …
例2: This means that … - ・トーンを抑える
例: These findings appear to prove that …
上の2つの例文では、断言することで疑いの余地を与えない動詞を使っています。このような言い回しは、研究結果の強調や、文献を引用する際に効果的な表現です。
一方、下の例文では2つの動詞を使っており、最初の動詞が2番目の動詞のトーンを抑えています。
<Example~形容詞>
- ・革新性: innovative, novel, cutting edge, pivotal
- ・重要性: extremely important, very significant
- ・確実性: clear, obvious, definite, undoubtedly
※他者の研究に対して使うのは問題ないが、自分の研究に使う場合は与える印象に注意する
また、形容詞にもこちらに示したような強いトーンを持つものがあります。このような形容詞を他者の研究に対して使うことは問題ありませんが、自分の研究に使う場合は、読者に与える印象に注意してください。
<Example~副詞・副詞句~>
- ・断定的な表現を和らげる
例1: X is somehow related to Y.
例2: X is likely related to Y. - ・主観性を和らげる ※多用すると曖昧になり過ぎるので注意!
例1: X was reasonably clearly visible.
例2: X was scarcely detectable, <´span>at least in our experiments. - ・類似性、相関性、整合性の程度を調整する
例: Our data fit quite well with those of Smith (2019).
さまざまな副詞を使って確信の程度を調整することも可能です。断定的な表現を和らげるときは、程度や可能性を示す副詞を使うことが有効です。また、主観的な表現に対しては副詞を足すことで動詞の強さを抑えることができます。類似性、相関性、整合性の程度を調整する際にも同じテクニックを使うことができます。
このように、直接的な表現を避けることで、読者の判断が入る余地ができ、読者からの反論を防ぐことができます。
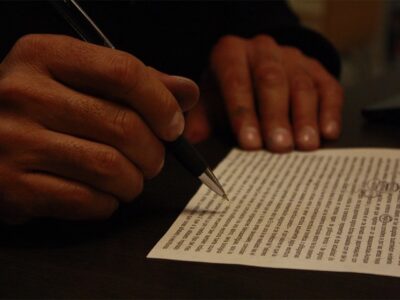
4.他者の研究成果に言及するとき
最後に、他者の研究成果に言及するときの注意点をお話いたします。
<Point ~他者の研究成果に言及するとき>
- ・他者の研究結果や結論に言及するときは、建設的な態度で、肯定的に扱う
- ・批評する内容を書くとき、although や however などの接続詞が効果的だが、使いすぎると否定的なトーンが強くなるため、注意する
- ・他者の研究成果に疑問を呈するとき、内容を全面的に否定するのではなく、他にも解釈の方法があることを述べる
例: A’s findings could also be interpreted as evidence of …. Viewed in this way, A’s results are actually in agreement with ours.
他者の研究結果や結論に言及するときは、相手に敬意を示すためにも、建設的な態度で、肯定的に扱うことが大切です。もし批評的な内容を書く場合は、althoughやhoweverなどの接続詞が効果的ですが、使いすぎると否定的な論調になるため、注意しましょう。また、先行研究の内容を全面的に否定するのではなく、下の例文のように、他にも解釈の方法があることを述べることで、肯定的に評価しましょう。
今回は、論文内で他者の研究について言及する際の注意点をお話しました。
次回は、「Part 11 剽窃と置き換え」としまして、適切に文献を引用するための注意点についてお話しします。ご拝読ありがとうございました。
- ★問い合わせ★
-
-
①臨床試験のお見積りに関するお問い合わせ
HP: https://orthomedico.jp/contact.html
Mail: info@orthomedico.jp -
②臨床試験に参加したい方はコチラ
HP: https://www.go106.jp/ -
③機能性表示食品の届け出に関するお問い合わせ
HP: https://届出.com/
Mail: planning-department@orthomedico.jp -
④栄養計算に関するお問い合わせ
HP: https://www.cand.life/
Mail: info@CAND.life -
⑤研究会の開催に関するお問い合わせ
HP: https://はじめての研究会.jp/
Mail: info@hajiken.jp
-
①臨床試験のお見積りに関するお問い合わせ
