シリーズ『おしえて論文作成』では、論文作成における留意点を紹介していきます。
教えて論文作成 Part 6-1では、あいまいな表現を避けー名詞・代名詞の注意点ーをご紹介します。

1.前回のおさらい
前回は「簡潔で無駄のないセンテンスを作ろう」としまして、センテンスの内容を簡潔にまとめ、要点を明確に伝える方法についてお話しました。
★前回のコラムは、こちら↓★
https://www.xn--79q34w.com/staff-blog/2023.02.03.1828/
常識的な情報や図表からわかることなどは本文で改めて言及せず、本質的・具体的な情報を速やかに提示することが大切です。
また、読みやすさを考え、できるだけ簡潔で文字数の少ない言葉を選びましょう。
その他、文法的なテクニックとして、動詞は名詞形よりもそのままの動詞を使うことや、It is … などの文が長くなりやすい表現の使用を避けることも有効です。
また、パラグラフの締めくくりは冗長にならないように注意しましょう。/
今回は、名詞や代名詞において、あいまいな表現を避けるためのヒントをお話しいたします。
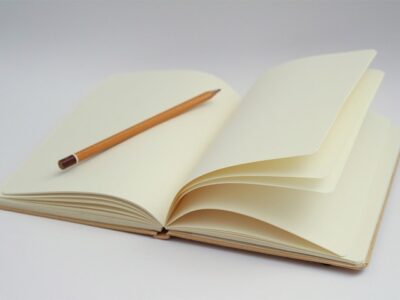
2.代名詞や同義語はあいまいさの原因!
はじめに、あいまいさの最大の原因となる代名詞や同義語についてお話します。
言語によっては名詞に格や性別が存在するため、代名詞が何を指しているのか明示することができます。
しかし、英語にはそのような仕組みがないため、代名詞が指す内容は読者に探してもらう必要があります。
<例文>
- 修正前:I put the book in the car and then I left it there.
- 修正後:I put the book in the car and then I left the book.
上の例文のitのように、itが何を指しているのか判断が難しい場合は、itの内容を具体的に示すことで、あいまいさを避けることができます。
英文を作成する際は、同じ文の中に同じ言葉を2回以上使ってはいけないと教わった方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、論文の中でキーワードとなる言葉を同義語で置き換えると、その言葉がキーワードを指していることに気づいてもらえない可能性が出て来ます。
そこで、同義語の使用はキーワード以外の形容詞や動詞に限定することが望ましいです。
ただし、前置詞はそれぞれ異なる意味を持つため、同義語を無理に探す必要はありません。
同じ前置詞が繰り返されても、文法的に正しければ問題ありません。

3.正確でわかりやすい用語を使おう
つづいて、用語の選定についてお話いたします。
論文では専門用語が出てくることも多いですが、読者は必ずしも専門家とは限りません。
<例文>
- 修正前:The homophily among humans introduces ….
- 修正後:The tendency of individuals to associate and bond with similar people introduces ….
そこで、上の例文のように、読者が理解できない専門用語は使わないようにし、その代わりに専門外の人にもわかるような説明に置き換えるとわかりやすくなります。
また、自分にとってはわかりやすい表現でも、読者にとってはそうでないこともよくあります。
そこで、下の例文のように、内容を具体的に示すことで、正確かつ十分な情報を与えると、わかりやすくなります。
<例文>
- 修正前:Climatic conditions were also checked.
- 修正後:Temperature and rainfall were also checked.
ただし、程度を表す形容詞や副詞は捉え方が個々の読者によって変わってしまうので、なるべく使わないようにしましょう。
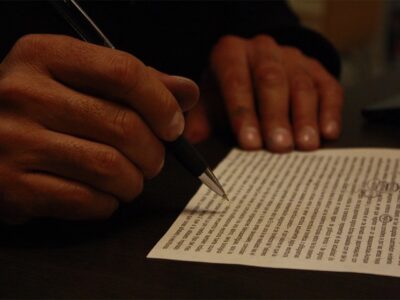
4.単語の関連性を明確にするコツ
次に、単語の関連性を明確にするコツをご紹介します。
通常、2~3の単語が連続していると、読者はそれらの単語が関連していると感じます。
<例文>
- 修正前:To obtain red colors, insects and plant roots were use by indigenous people
- 修正後:Insects and plant roots were used to obtain red colors.
上の例文では、文を最後まで読まないと、red colorsとinsectsが一連の語句のように思われる可能性があります。
修正後の例文では語順を変え、どの単語が関連しているのか明確にしたことで、読みやすくなっています。
また、句読点やハイフンを使うことでも単語の関連性を明確にすることができます。
下の例文では、「車はあるがほとんど乗らない」なのか「中古車を所有している」なのか判断することができません。
<例文1>
- 修正前:I have a little used car in the garage.
- 修正後:I have a little-used car in the garage.
修正後の例文では、ハイフンを使って単語の関連性を明らかにしたことで、文意がはっきりしました。
このように、単語が連続している箇所では、関連性が明確になっているかよく確認しましょう。

5.関係代名詞の利用
先行詞は不特定の人や物の場合が多く、関係代名詞節で先行詞を具体化・特定化する
(関係代名詞)
-
- 制限用法
-
- •先行詞は不特定の人や物の場合が多く、関係代名詞節で先行詞を具体化・特定化する
- •科学英語ではthatを使う
例: My sister that lives in Paris is a teacher.
-
- 非制限用法
-
- • 先行詞はすでに特定された人や物の場合が多く、コンマに続く関係代名詞節で情報を補足的に追加する
- • 先行詞が物の場合はwhich、人の場合はwhoを使う
例: I have a son, who lives in Tokyo.
最後に、情報の追加によく使われる関係代名詞についてお話いたします。
関係代名詞には制限用法と非制限用法が存在するということはご存じの方が多いかと思います。
制限用法は、不特定の人や物を先行詞にとり、関係代名詞節を使って具体化、特定化する用法です。
科学英語では、上の例文のようにthatを使います。
非制限用法は、すでに特定された人や物を先行詞にとり、コンマに続く関係代名詞節を使って情報を補足する用法です。
先行詞が物の場合はwhich、人の場合はwhoを使います。
関係代名詞はその直前に置かれた名詞を修飾しますので、下の例文のように先行詞と関係代名詞節が離れてしまうと意味の取り違えが生じる可能性が高くなります。
<例文>
- 修正前:Each event is characterized by a set of parameters,
as reported in Table 1, which describes …. - 修正後:Each event is characterized by a parameters as
reported in Table 1. This set describes ….
そこで、語順を工夫したり、必要に応じて文を分割するなどして文意があいまいにならないように工夫しましょう。
今回は、あいまいな表現を避けるために、名詞や代名詞を使う際に気を付けることについてお話しました。
次回は、「Part 6 あいまいな表現を避けよう」の後半としまして、文法上の注意点についてお話しします。
ご興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。
ご清聴ありがとうございました。
- ★問い合わせ★
-
-
①臨床試験のお見積りに関するお問い合わせ
HP: https://orthomedico.jp/contact.html
Mail: info@orthomedico.jp -
②臨床試験に参加したい方はコチラ
HP: https://www.go106.jp/ -
③機能性表示食品の届け出に関するお問い合わせ
HP: https://届出.com/
Mail: planning-department@orthomedico.jp -
④栄養計算に関するお問い合わせ
HP: https://www.cand.life/
Mail: info@CAND.life -
⑤研究会の開催に関するお問い合わせ
HP: https://はじめての研究会.jp/
Mail: info@hajiken.jp
-
①臨床試験のお見積りに関するお問い合わせ
